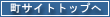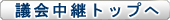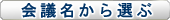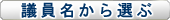※本会議の録画映像をご覧いただけます。
eyJwbGF5ZXJLZXkiOiJjYmJlMDljOS0yYzc0LTQwNDEtOWJkNC1iYjZlY2UzYjk0MDAiLCJhbmFseXRpY3NLZXkiOiI5ZWM4YTVlMS1lNWNkLTRkMzUtYTFlMC0wOTE4MWYzOTQwMDYiLCJpc0xpdmUiOmZhbHNlLCJ0aXRsZSI6Imthd2FzYWtpLXRvd25fMjAyNTA2MTFfMDA2MF90ZXJhZGEtaGliaWtpIiwicGxheWVyU2V0dGluZyI6eyJwb3N0ZXIiOiIvL2thd2FzYWtpLXRvd24uc3RyZWFtLmpmaXQuY28uanAvaW1hZ2UvdGh1bWJuYWlsLmpwZyIsInNvdXJjZSI6Ii8va2F3YXNha2ktdG93bi5zdHJlYW0uamZpdC5jby5qcC8/dHBsPWNvbnRlbnRzb3VyY2UmdGl0bGU9a2F3YXNha2ktdG93bl8yMDI1MDYxMV8wMDYwX3RlcmFkYS1oaWJpa2kmaXNsaXZlPWZhbHNlIiwiY2FwdGlvbiI6eyJlbmFibGVkIjoiZmFsc2UiLCJwYXRoIjoiIn0sInRodW1ibmFpbCI6eyJlbmFibGVkIjoiZmFsc2UiLCJwYXRoIjoiIn0sIm1hcmtlciI6eyJlbmFibGVkIjoiZmFsc2UiLCJwYXRoIjoiIn0sInNwZWVkY29udHJvbCI6eyJlbmFibGVkIjoiZmFsc2UiLCJpdGVtIjpbIjAuNSIsIjEiLCIxLjUiLCIyIl19LCJza2lwIjp7ImVuYWJsZWQiOiJmYWxzZSIsIml0ZW0iOlsxMF19LCJzdGFydG9mZnNldCI6eyJlbmFibGVkIjoiZmFsc2UiLCJ0aW1lY29kZSI6MH0sInNlZWtiYXIiOiJ0cnVlIiwic2RzY3JlZW4iOiJmYWxzZSIsInZvbHVtZW1lbW9yeSI6ZmFsc2UsInBsYXliYWNrZmFpbHNldHRpbmciOnsiU3RhbGxSZXNldFRpbWUiOjMwMDAwLCJFcnJvclJlc2V0VGltZSI6MzAwMDAsIlBsYXllclJlbG9hZFRpbWUiOjMwMDAsIlN0YWxsTWF4Q291bnQiOjMsIkVycm9yTWF4Q291bnQiOjN9fSwiYW5hbHl0aWNzU2V0dGluZyI6eyJjdXN0b21Vc2VySWQiOiJrYXdhc2FraS10b3duIiwidmlkZW9JZCI6Imthd2FzYWtpLXRvd25fdm9kXzUwMDMiLCJjdXN0b21EYXRhIjp7ImVudHJ5IjoicHVibGljIn19fQ==
- 令和7年度第2回川崎町議会(6月定例会議)
- 6月11日 本会議 一般質問
- 寺田 響 議員
1.教育施策について(子どもの居場所)
① 現在、子どもに関する課題は複雑化、複合化している。児童虐待相談件数、不登校児童生徒数、児童生徒の自殺者数が増加傾向にあり、その原因は一つに特定することができません。そうした現状を踏まえたうえで、今後の子ども政策の基本理念は「全ての子どもが、安全で安心して過ごせる多くの居場所」を持つことが求められます。また、こども家庭庁は子どもの居場所について、図書館は全ての子ども、若者を対象とした居場所であると述べている。公共図書館が居場所としての機能を持つことにより、子ども達は安心することができ、自由に学ぶことができる場所と機会を得る。子どもが一人でかつ無料で滞在することが許され、利用者の秘密を守る図書館は、居場所としての要素が備わっている。そのため、図書館はその役割を果たす責任があると考える。しかし一方で、図書館は公共の場所であり静かに本を読みたい・探したい方がたくさんいます。そういう方にとっては子どもの叫び声、集団でのおしゃべりの声は邪魔になります。川崎町立図書館(パピルスホール)でも同様な問題が起きています、図書館の今後について教育長の考えを伺います。
② 令和5年10月31日(木)発表の「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」によると福岡県は小学生7328人(全国5番目)、中学生10820人(全国7番目)になります。不登校が長期化すると、学業の遅れが大きくなり、高校卒業やその後の進路に影響を及ぼす可能性があります。また、学校という社会との接点がなくなることで、コミュニケーション能力が低下したり、孤独感を深めたりするなど、精神的な問題を抱えるリスクも高まります。不登校は毎年増加傾向にあり町の重要課題であります。また、令和5年4月こども家庭庁が発足、こども基本法が施行されました。背景として、児童虐待やいじめ、不登校等子どもを取り巻く状況が深刻であることが一因のためです。川崎町においても平成18年策定された(子どもの権利条例)では、官民一体で子どもたちの問題に取り組むとされています。特に川崎町では小学校中学校における不登校児童の多いことが懸念されます。地域、社会、大人の力を合わせ、未来の担い手である子どもたちの育ちに全力で取り組む時が来たのではと思い(居場所づくり地域づくり)が必要と考えますが、不登校対策について教育長の考えを伺います。
① 現在、子どもに関する課題は複雑化、複合化している。児童虐待相談件数、不登校児童生徒数、児童生徒の自殺者数が増加傾向にあり、その原因は一つに特定することができません。そうした現状を踏まえたうえで、今後の子ども政策の基本理念は「全ての子どもが、安全で安心して過ごせる多くの居場所」を持つことが求められます。また、こども家庭庁は子どもの居場所について、図書館は全ての子ども、若者を対象とした居場所であると述べている。公共図書館が居場所としての機能を持つことにより、子ども達は安心することができ、自由に学ぶことができる場所と機会を得る。子どもが一人でかつ無料で滞在することが許され、利用者の秘密を守る図書館は、居場所としての要素が備わっている。そのため、図書館はその役割を果たす責任があると考える。しかし一方で、図書館は公共の場所であり静かに本を読みたい・探したい方がたくさんいます。そういう方にとっては子どもの叫び声、集団でのおしゃべりの声は邪魔になります。川崎町立図書館(パピルスホール)でも同様な問題が起きています、図書館の今後について教育長の考えを伺います。
② 令和5年10月31日(木)発表の「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」によると福岡県は小学生7328人(全国5番目)、中学生10820人(全国7番目)になります。不登校が長期化すると、学業の遅れが大きくなり、高校卒業やその後の進路に影響を及ぼす可能性があります。また、学校という社会との接点がなくなることで、コミュニケーション能力が低下したり、孤独感を深めたりするなど、精神的な問題を抱えるリスクも高まります。不登校は毎年増加傾向にあり町の重要課題であります。また、令和5年4月こども家庭庁が発足、こども基本法が施行されました。背景として、児童虐待やいじめ、不登校等子どもを取り巻く状況が深刻であることが一因のためです。川崎町においても平成18年策定された(子どもの権利条例)では、官民一体で子どもたちの問題に取り組むとされています。特に川崎町では小学校中学校における不登校児童の多いことが懸念されます。地域、社会、大人の力を合わせ、未来の担い手である子どもたちの育ちに全力で取り組む時が来たのではと思い(居場所づくり地域づくり)が必要と考えますが、不登校対策について教育長の考えを伺います。